子どもの教育にどれだけお金をかけるかというのは、とても悩むことです。
我が家の場合、地域の学校環境やお財布事情を考慮すると、子ども達は中学までは、地域の公立学校に通うと思います。
塾通いも、いまは考えていません。
でも、時間もたっぷりあるし、スポンジのようにいろいろな事を吸収できる小学生時代。
何もしないのはもったいない!
幸い長男は、いろいろなことに興味を持ち、たくさんの質問をしてくれます。
それなら日常生活の中で、子どもの興味が広がるような工夫をしてみようと思いました。
スポーツ観戦で世界地図を学ぶ
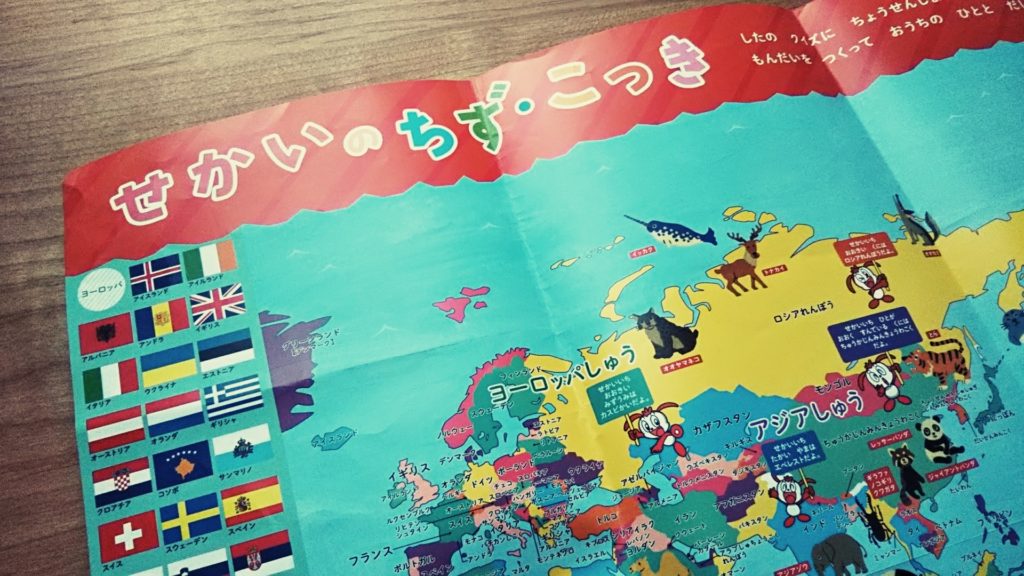
いろいろなスポーツのテレビ中継で、日本代表の対戦相手国を、
「この国はどこにあるの?」
と聞いてくれます。
特にサッカーは、日常ではあまり知る機会のない、さまざまな国が登場しますよね。
ウズベキスタン、キルギス、トルクメニスタン…。
わたしもどこにあるか知らない国が多くて…(特に旧ソ連は難しい!)。
一緒に世界地図を広げて探します。
ラグビーワールドカップのときは、日本以外の試合もテレビで中継していました。アイルランドとか、ニュージーランドとか。
あれ?アイルランドってイギリスとは別の国だっけ?
(あいまいな知識が、なんと多いことか!)
子どもは遊び感覚、勉強しているのはわたしのほうだったり…(笑)
ほかには、名前が似ている国を探してみたり(オーストリアとオーストラリア、インドとインドネシアなど)。
暗記しようとしているわけでもなく、遊びの延長でしかないのですが、改めて世界について学ぶ時に、「あ~、あのとき見た!」と思ってくれたらうれしいです。
食べ物で分数を学ぶ

「数」の感覚を身に付けるとき、母親は食べ物で教えるのが手っ取り早いですよね。
足したり引いたり分けたり、なんでもできます。
中でも分数は、ケーキを切り分けるとき。
1個のケーキを4つに切るか、6つに切るか…。
そのうち、ボクは何個食べられるか…。
そんな話をしているなかで、「あ、これって分数だな」と思い、
「4つに切って1つ食べたら、4ぶんの1だね」と。
4ぶんの2と、2ぶんの1が同じであることも、これなら約分を知らなくても理解できます。
買い物で足し算・引き算を学ぶ
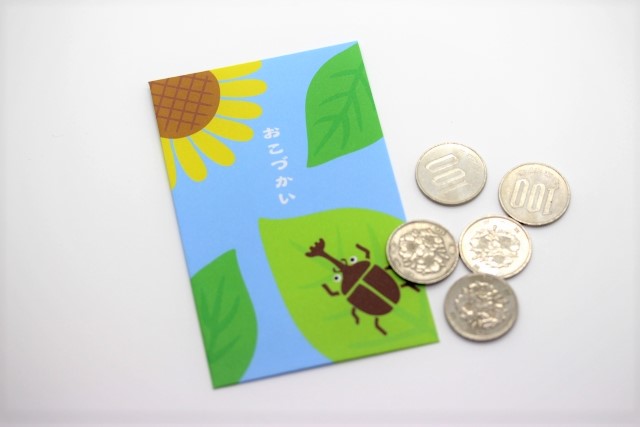
一般的には、何歳くらいからおこづかいを渡して、自分で買い物をさせるのでしょうか?
とあるアンケート調査を見てみたところ、小学校1年生でおこづかいをあげているのは少数派。3年生くらいから渡しはじめるご家庭が多いようです。
我が家もまだ決まったおこづかいを渡していませんが、つい最近、地域のお祭りがあったので、1000円を渡して、自分で買い物をさせてみました。
お祭りを選んだのは、200円、300円と切りのいい数字で買えるものが多いから。
自分の食べたいものはいくらなのか?
1000円で収めるには、どうしたらいいか?
考えながら買い物していました。
長男が選んだのは
- からあげ 300円
- ポテト 300円
- かき氷 300円
- ゲーム 200円
100円オーバーしてしまいました(笑)
(お祭りも、まともに買い物すると結構出費しますね…)
世界のナベアツで九九を学ぶ

子どもって、インパクトのある単純なネタが大好きですよね!
長男も、TT兄弟とか、そんなの関係ねぇ(いまごろ)とか、よくマネしてやっています。
で、ふと世界のナベアツさんの「3と3の倍数でアホになる」ネタを思い出して、Youtubeで見つけて一緒に観てみました。
面白かったみたいで、そのあと、わたしと長男、次男(0歳)と3人でアホになる遊びをしました。
楽しかったです(笑)
まとめ:好奇心があれば、お金をかけなくても勉強できる!
長男は、チャレンジ1年生をやっていますが、そこで学ぶことは、学校の授業の延長です。
予習復習はできるけど、1年生が習う予定がないことを学習することは、まずありません。
でも、世界の国とか、分数とか、かけ算とか、きっかけさえあれば1年生でも(全てではないけれど)理解できる部分もあるんだなと、日々実感しています。
勉強が堅苦しいものではなく、自分の生活と密着していることを知って、好奇心を伸ばしてほしいな~と思っています。
合わせて読みたい



コメント