小1の2学期からはじまった漢字の学習。
11月半ば迄で習った漢字は40個とちょっと。
たったこれだけしか習っていなくても、習った漢字をヒントに、どんどん新しい漢字に興味を持ちはじめました。
そして、長男の漢字を覚える様子を見ていて、「なるほど~」と感心したことがあります。
習った漢字は生活の中で復習
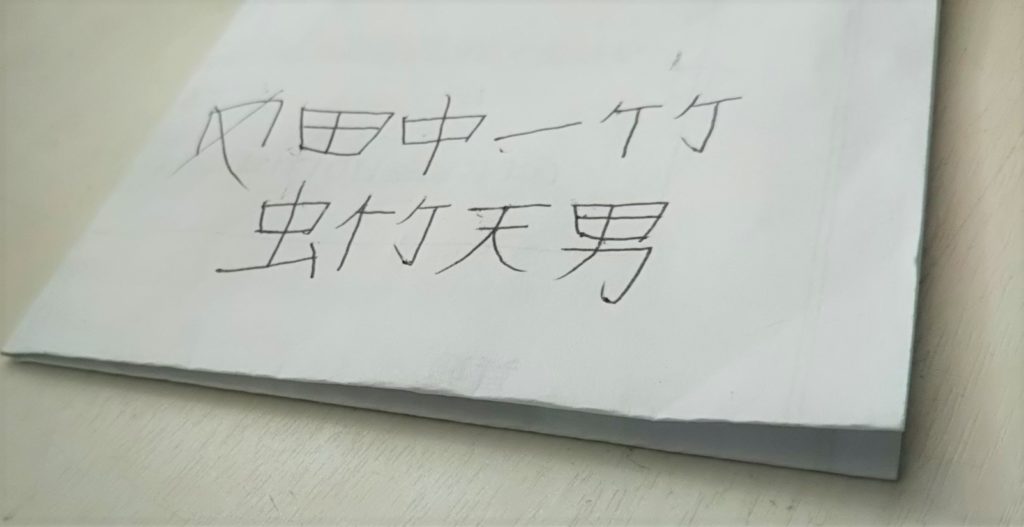
長男は、テレビで習った漢字を見つけるたびに、
「空!」
「中学!」
「田中!」
と叫んでいます。
生活のなかで自分が覚えた漢字を確認するは、いちばんいい復習方法だなと感心しました。
習う前の漢字も芋づる式に覚えられる
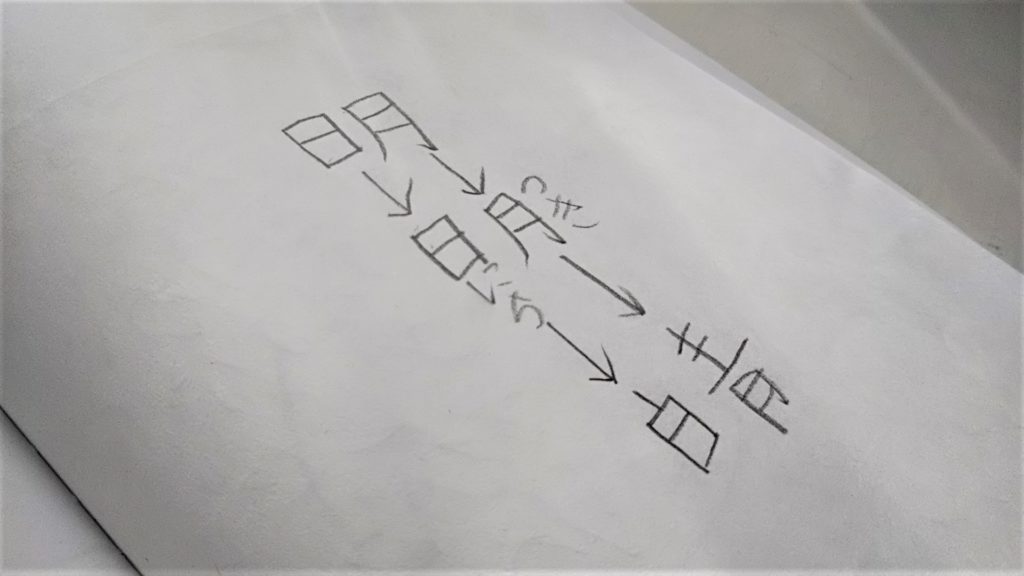
すると、今度は習っていない漢字でも、「これ何て読むの?」と、いろいろ質問してくるようになりました。
「○○って読むよ」と長男に付き合うようになると、そこには覚えやすいルールがあることに気付いたのです。
形が似ている漢字
「大と木と本って似てるよね」
「人と入って逆だよね」
「正のなかに止があるね」
とか、まだ覚えたてだったり、読めなかったりするからこそ、形の共通点に気が付きやすいようです。
「正しい」と「止める」は、意味も読み書き順も違う。
文字として読めてしまう大人の方が、その共通点には気付きにくいものです。
でも、子どもにとっては図形の間違い探しみたいに見えるのかも。
漢字は、ものの形が発展してできたものなので、形から入るのは間違いではない!と思いました。
組み合わせてできる漢字
次に長男が気になったのは、習った漢字が一部に使われている漢字。
それが「へん」や「つくり」であるという認識はないけど、「覚えた字がくっついている漢字が、どうやらたくさんありそうだ」ということに気付いたようです。
長男「日と月でなんて読むの?」
わたし「『あかるい』だよ、太陽と月があると明るいでしょ?」
長男「木の横に何かくっついてる」
わたし「それで村だよ」
長男「村と町ってなにが違うの?」
わたし「うーん…、村の方が、田舎?」
芋づる式に、素朴な疑問が飛んでくることも多く…。
(あとで調べたら、市、町、村の違いは人口の違いでした!)
パターンが同じ漢字
長男「オレ、『てじな』の『手』、書けるよ!」
わたし「じゃあ問題。『てじな』の『しな』は、ある漢字を3つ組み合わせるとできるよ。さて何でしょう?」
長男「分かんない!」
わたし「正解は、口でした」
長男「分かった!森みたいに書くんでしょ?」
ちょうど、森を習った直後だったから、3つ書くと聞いてピントきたようでした。
ほかにも探すと、同じ形を繰り返す文字には「多」「炎」などがあったり…。
暮らしの中の生きた漢字は定着しやすい
長男を見ていると、教科書やドリルに整列して並んでいる漢字より、家の中で見かける漢字を覚えるほうが、定着しやすいように思いました。
我が家は、よくないと思いつつも、夕飯時はついテレビをつけてしまうのですが、知っている漢字に反応して、そこから言葉の使い方を学べることも。
それならば、息抜きプラス、知識を広げる時間にしてしまってもいいかも!と思いました。
学びの旬を逃さない
4人の子どもを東大理Ⅲに入学させた佐藤亮子ママが、「学びには旬がある」とおっしゃっていました。
旬とは、学んだことを吸収しやすい時期があるということ。
長男にとって、いま、漢字は発見の連続。
長男「カタカナを練習すれば漢字が上手くなるんだよ」
わたし「どうして?」
長男「だって、タとロで『名』だし、田とカで『男』でしょ?」
その覚え方の良し悪しは別として、そうやって発見しながら覚えるって、とても大切な気がする。
一方で英語には、今のところ興味なし。
何でも吸収しやすい時期だから、やれば覚えるだろうけど、やっぱり興味のあることを覚える方が楽しいし、親もサポートしやすい。
いまは漢字が旬ということで、付き合いたいと思っています。
合わせて読みたい
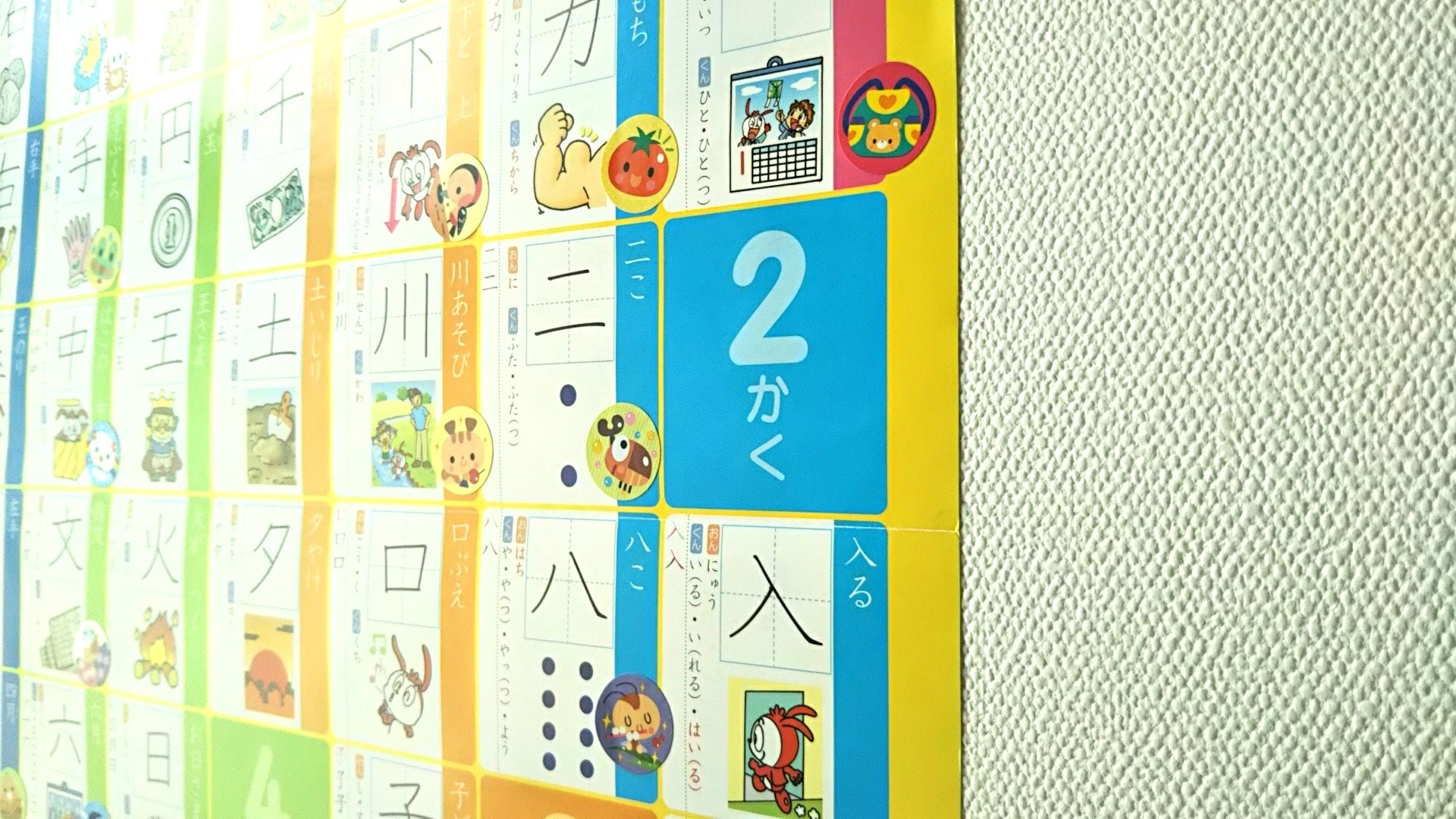

コメント