我が家は大きな河川のそば、洪水浸水想定地域に住んでいます。
2019年の台風19号ではじめての避難指示(レベル4)が出て、当時0歳と7歳の子を連れて避難を経験しました。
それ以来、洪水浸水想定地域に住む上で、どんな備え、心構えをしておけばよいか真剣に考えるようになりました。
ここでは、避難経験を踏まえて洪水浸水想定地域に住む人々の備えについてまとめてみました。
日頃の備え
天気予報をみる
当然過ぎることですが、基本なのであえて最初に書いておきます。
できれば遭いたくない台風や豪雨ですが、唯一有り難いのは、地震とは違い、あらかじめ予測がしやすいこと。
天気の異変の事前チェックが欠かせないのは、子ども達が小さいなら尚更です。
我が家は、平日は、保育園(次男)、小学校(長男)、職場(わたし)、市外の職場(旦那)とみんなバラバラの場所で過ごしています。
台風や豪雨がいつ接近するかで行動が変わります。
だから、日頃から天気予報はまめにチェックしています。
最近は、天気が良くても急に竜巻注意報が出ていたりするのも気になります。
避難できる場所を複数用意しておく
我が家では、避難できそうな場所を3つ想定しています。
- 最寄りの避難所(小学校)
- 少し離れた高台にある避難所
- 電車で行ける知人の家
なぜ3つも考えているかというと、家が浸水するとしたら、最寄りの避難所も浸水するはずだから。
状況によっては、避難所として開設されない場合もあります。
それでも第1候補は最寄りの小学校で、ここには台風19号で実際に避難しました↓
小学校は、子どもが通学している学校で馴染みがあるし、いざというとき上階へ逃げれるのも安心です。
ちなみに本当にいちばん近い避難所はコミュニティセンターですが、2階建てで狭いので行くのはやめました。
第2候補は高台にある浸水想定区域外の避難所。ここへは、車でも約10分。徒歩なら30分以上かかるので、暴風雨のときはとても歩けません。
なので、仮にここへ避難するとなると、かなり早い段階から移動する必要があります。
第3候補は、電車で30分くらいのところに住む知人の家。
この知人は、我が家が台風19号で避難したと話すと「今度避難することがあったら、うちに来ていいからね!」と有り難くも言ってくれた人。
浸水とは無縁の場所なので、本当に困ったときは好意に甘えるつもりです。
でも、台風19号のときは、早くから交通機関の計画運休が決まり移動に制限がでました。
本当にお世話になるとしたら、「一体どんなタイミングになるだろう?」と難しさも感じています。
ちなみに台風19号のときの周囲の行動は、
- 自宅にとどまった人
- 避難所へ移動した人
- 親戚の家に移動した人
の3パターンでした。
どの行動がベストかは、実際にそのときになってみないと分からないもの。
それでも、いざというときに身を寄せられる場所が1つではないことで少し安心できます。
ライフジャケットを購入しておく
「そこまでいる?」と最初は思っていましたが、2018年の西日本豪雨、2019年の台風19号で、屋根の上で救助待ちをしている映像を何度も見ているので、決して他人事とは思えません。
次男が生まれたのを機に、家族4人分購入しました。
「ライフジャケットって高そう…」と思っていましたが、価格はピンキリ。
商品テストサイトで高評価だった物のなかに、安い商品があったのでネットで購入しました。
1着1,700円くらい。4着で7,000円以下。
いざというときの備えがこの値段ならまぁOKかなと。
海のレジャーにも使えます。
ちなみに購入したライフジャケットはこちらですが…、値上りしています Σ(・□・;)
防災グッズは2階に置く
防災グッズは、基本2階に置くようにしました。
- 非常用持出袋
- ライフジャケット
- 備蓄水
- 備蓄用の食料(乾パン)
リビングが1階なので、非常時に必要なものすべてを2階に置くのは難しいのですが、最低限のものだけでも上階に集めました。
屋根への上り方を考えておく
垂直避難のいちばん上は屋根。
でも、みなさんどうやって屋根に上っているのでしょうか?
我が家の場合は、ベランダから、長めの脚立かはしごを使えば、何とか上れそうです。
あとは、衣装ケースとかを積み上げれば子どもでも何とか上れるかも?
でも、本当に屋根に逃げなきゃならないときに、そんな時間はなさそうです…。
もっとも、そんな事態になる前に避難所にいたいのが本音…。
台風・豪雨が近づいてきたら
河川の増水をチェックする
注意したいのは、実際に見に行かないこと。
川の水位やライブ画像を見れるサイトがいくつかあります。
国土交通省のサイトは地域を選択して全国の情報を知ることができます。
都道府県でも同様の情報を取りまとめていたりします。
神奈川県はこのサイトで河川の水位やライブ画像、ダム放流情報を知ることができます。
Yahoo!の防災速報アプリを使えば、指定地域の警報などをプッシュ通知で受けとることができます。
大事なものはできるだけ2階へ移動
これは時間に余裕があるときですが、高価なもの、代わりの効かないものは、優先順位をつけて上階に移動。 我が家の場合は、
- パソコン
- ランドセル
- 楽器
家にとどまる場合もですが、避難する場合も、万が一の浸水を考えるとやっておきたいです。
早めに避難準備をはじめる
「これは避難情報が出そうだ…」となったら、とにかく、無駄になってもいいので早めに準備をはじめることが肝心です。
災害発生前の避難なので、“着のみ着のまま”という訳にはいきません。
万が一、浸水したらすぐには帰れないと考えると、泊まれる準備も必要です。
我が家は避難用袋を常備していますが、台風19号でいざ「避難所へ行くぞ!」となると、それだけでは全く持ち物が足りませんでした。
というか、事前避難に必要な持ち物は、非常用品よりも、いわゆるお泊まりセットに近いものでした!
「えっと、子どもの着替え、オムツ、食料、常備薬…」
「あれ、通帳とかも持っていった方がいいのかな…」
そうこうしているうちに警戒レベル3からレベル4:避難指示(緊急)に切り替わったので、荷物を取捨選択する間もなく、大荷物を抱えて避難するハメに…。
避難しやすいように荷物をコンパクトにまとめることも大切だと思うのですが、それが全くできなかったのが、はじめての避難の反省点でした。
避難情報が出はじめてから「あら大変!」と準備をはじめると焦ります。
無駄になっても、それはそれで「よかったね」と思えばいいだけの話なので、準備は落ち着いてできるうちに、ある程度済ませておくと冷静な判断がしやすいです。
早めに避難する
準備が早めに済めば、避難も早めに出来ます。
空振りを恐れる必要はどこにもありません。
実際、台風19号のとき、わたしの住む地域では幸いにも被害がありませんでしたが、「避難が無駄だった」とか「避難して損した」とか微塵も感じませんでした。
確かに避難所で一夜を過ごすのは決して快適とはいえません。
でも、避難所に入る情報は正確で、しかも早い。行動判断も自分たちだけで決める必要がないので、精神的にとても楽というメリットもありました。
心配しながら家に残るくらいなら、空振りでも避難してしまったほうが安心です。
特に、自分で歩けない乳幼児や高齢者がいるご家庭は早めの避難をおすすめします。
まとめ:洪水浸水想定区域に住む人が逃げ遅れないための備え9ヵ条
以上、洪水浸水想定区域に住む人が備えたいことをまとめてみました。
~日頃の備え~
1.天気予報をみる
2.避難できる場所を複数用意しておく
3.ライフジャケットを購入しておく
4.防災グッズは2階に置く
5.屋根への上り方を考えておく
~台風・豪雨が近づいてきたら~
6.河川の増水をチェックする
7.大事なものはできるだけ2階へ移動
8.早めに避難準備をはじめる
9.早めに避難する
いちばん安心できるのは、避難のする必要のない場所に引っ越すことだけど、我が家のように家を建ててローン返済中だったりすると、すぐにそういうわけにもいかないのが現実です。
だから、避難経験をもとに実際に何が出来るかを考えてみました。
今年が避難の必要のない1年であることを祈りつつ、この記事を終わりたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
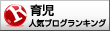




コメント