こんにちは!
6歳差兄弟を育てる2児の母・ひまわりと申します。
新型コロナウイルスの広がりから、家庭学習のニーズが高まっているところですが…。関連記事⇒【コロナで自宅学習に役立つ通信教育】チャレンジはここが便利
この記事では、長男が小1のときに進研ゼミのタブレット教材「チャレンジタッチ」をはじめることになった理由と、使ってみての感想をまとめています。
チャレンジはやめるつもりだった我が家
取り組み方が気になったこどもチャレンジ
年中からこどもチャレンジをやっていた長男でしたが、1年生になったらやめるつもりでいました。
なぜかというと、だんだん親に促されないとやらなくなったから。
はじめた頃は、毎月届くのを楽しみにしていて、ワークも本も端から端までこなしていました。
でも、年長になってだんだん慣れてきたのか、着手が遅れ気味に。
「自分からすすんでやる」から「親が促せばやる」に。
「楽しいもの」から「やらなければならないもの」に変わってきたように思えました。
勉強は、いやいややっても意味がない。
「やらされている」という感覚が習慣化するのは避けたいと思いました。
だから、「1年生のうちは、学校の勉強と宿題に集中させよう」と思い、年長のうちに、チャレンジ1年生は停止してしまいました。
(停止しなければ、そのまま届き続けます)
自ら「やりたい」と意思を持つ大切さ
ところが入学前の2月頃、長男自ら
「いちねんせいになっても、つづけたい」
と言ったのです。
「それであれば、続けてみたらいい!」
と再契約。
1度解約してしまったことでひと手間かかってしまいましたが、それよりも、子ども自身の意思をはっきり確認できたことが大きかったです。
小1はチャレンジタッチにした理由
「ゲームやりたい」
と言うようになった長男。
ゲーム機はまだ買わないつもりだけど、チャレンジタッチのタブレットならOKかなと勧めてみました。
しかし意外にも、
長男「紙のほうがいいかな…」
わたし「どうして?」
長男「…なんとなく」
紙がいいと言いつつも、タブレットも捨てきれず、どちらにも決めきれない様子でした。
最終的には、ベネッセのサイトにある「学習スタイル診断」を参考にしながら、わたしの判断でチャレンジタッチにしました。
具体的には次のような理由からです。
取り組みやすさを優先
チャレンジとチャレンジタッチ。
公式サイトの比較を見ると、紙のテキストで学ぶチャレンジの方が、学力は伸びそうでした。
しかし、「親が声をかければ机に向かう」という状態だった長男。
小学校の勉強や宿題に、どんな風に取り組む子なのか、親にも想像がつかない部分がありました。
だからまずは、机に向かう習慣作りを大切にしたい。
チャレンジタッチは、少々気分が乗らなくても、電源を入れれば、音声で導いてくれます。
取りかかりが心配な場合は、紙教材よりスムーズに勉強モードに誘導できるかな?と思いました。
音声のサポートがある
こどもチャレンジのワークは、わたしが隣に座って取り組んでいました。
わたしが問題を読む係。
しかし、長男が小1になったとき、次男はまだゼロ歳。
同じように、隣に座ってみてあげられるか分からない状態でした。
チャレンジタッチなら、親の代わりにコラショ(ランドセルのキャラクター)が勉強を進めてくれます。
丸つけ機能もあり、間違えた問題だけ解き直しも案内してくれます。
親の都合で子どもを待たせなくてよい点が気に入りました。
ゲーム要素がある
毎月、決まった日に新しいアプリが届きます。
ゲームに興味を持ちはじめていたので、遊び感覚で学習できるのも、取り組むきっかけになると思いました。
「ゲーム機の代わりにコレで満足してくれたらな…」と思ったのですが、それはムリでした(笑)
紙だと整理が大変
これは親の都合ですが…。
こどもチャレンジ時代、毎月届く教材を整理するのが結構手間で…(笑)
子どもは楽しみにしていましたが、片付けは親の仕事…。
チャレンジタッチなら、教材は基本ダウンロードなので、ほぼペーパーレス(年に数回は郵便が届きます)。
親のストレスを1つ減らせます。
***
これらの予想はだいたい当たっていて、学習習慣は1年生の1学期うちに付いたと思います。
べったり横に付いていなくても、料理をしながら、分からないところだけサポートするという関わり方もできました。
アプリは興味のあるものだけ使っていましたが、足し算引き算は、パズルやレースゲームで楽しく予習復習していました。
郵便物が少ないのも助かりました(わたしが)。
でも、良い点も悪い点も表裏一体。
タブレット学習の弱点も分かりました。
チャレンジタッチ(タブレット学習)のデメリット
文字を書く練習にはなりにくい
鉛筆で紙に書くのと、タッチペンでタブレットに書くのでは、手応えが全く違います。
まだ字を書くことに慣れていない子どもが、タブレットに文字を書くのは、なかなか難しいです。
はじめのうちは、慣れないなか、とても丁寧に書いていました。
「とめ」や「はらい」がいい加減だと、マルがもらえないんですね。
ところが、だんだん慣れてくると、今度は雑に書くようになっていきました。
ポイントを押さえて書けば、丁寧に書かなくてもオッケーがもらえることに気付いてしまったのです(笑)
だから、文字を覚えることには役立ったけど、書く練習になったのかは疑問です。
文字を認識してくれないとイライラする
子どもの書くぎこちない文字だと、肉眼では確実に読めて、はね、はらいにも注意しているのに、なかなかマルがもらえないときがありました。
何度書いても別の文字と認識されたことも。
いまだに、何がダメだったのかわかりません。
ただ、そういったことは、4月、5 月のはじめの頃に少しあっただけで、子どもが使い慣れてくると、なくなりました。
そうは言っても、慣れないなか一生懸命書いた文字がバツになるので、そのときはとてもイライラしていました。
フリーズすることがある
機械なので、どうしてもこういった不具合は出てきます。
せっかく解いた問題が、フリーズしてやり直しになったことも。
紙の学習とは別の種類の忍耐力は付くかも(笑)
読解力は鍛えにくい
音声がサポートしてくれるので、自分で問題を読む力は、紙のテキストと比べると付きにくいと思います。
長男の場合、学校のテストで、問題を読み違えて不正解になることがまたにあったので、そこは今後の課題でした。
それでも小1はチャレンジタッチにしてよかった理由
上記のようなデメリットも感じつつ、それでも我が家はチャレンジタッチを選んでよかったです。
学習習慣が身に付いた
チャレンジタッチをはじめたいちばんの目的、「学習習慣」は身に付いたと思います。
今日はどこから勉強をはじめるかなどは、タブレットが案内してくれるので、受け身なところはありますが、机に向かうことは出来るようになったと思います。
授業の予習復習に役立った
学校で習う勉強の予習復習であれば、チャレンジタッチで十分対応できます。
文字を覚えることも、足し算引き算も繰り返しやることが大切だと思うので、その点は、宿題プラスアルファの勉強として役に立ったと思います。
学校で使用する教科書に対応しており、教科書の内容を先取りしておけたので、スムーズに授業に臨めたのでは?と想像しています。
学習量が調整できる
過去のチャレンジタッチのレビューを見ると、「すぐ終わって勉強にならない」という感想が多数ありますが、2019年現在は、改善されていると思いました。
メインレッスン(基本のレッスン)は、無理なく終わるボリュームなので、毎日やれば月の後半は、確かにやることがなくなってしまいます。
しかし、引き続き演習問題で同じように勉強できるので、そこは問題ありませんでした。
我が家はメインレッスンのみ必達課題にして、演習問題は強制せず、余力があるときだけやっていました。
親より上手に教えてくれる
絵が動いて計算の仕方を解説してくれるので、繰り上がり算などの計算のコツが分かりやすかったです。
「こうやって教えてあげるといいんだ~」と勉強になりました。
まとめ:チャレンジタッチをおすすめしたい方
それぞれ良い点があるタブレット学習と紙ベースの学習。
子どもがやりたい方が選ぶのが、いちばんだと思いますが、迷ったときは、その子の勉強への取り組み方や、何を期待するかで選らんでみるとよいと思います。
わたしが思う、チャレンジタッチをおすすめしたい方(親目線)は、
- 子どもに学習習慣を身に付けさせたい方
- 学校の予習復習や基礎学力の定着を目的にしたい方
- 勉強をサポートする時間がない方
- 勉強のサポートに自信がない方
合わないかな?と思えば変更もできます。
実は我が家も子どもと相談して、2年生からは紙の学習へ切り替えることを決めました。

合わせて読みたい



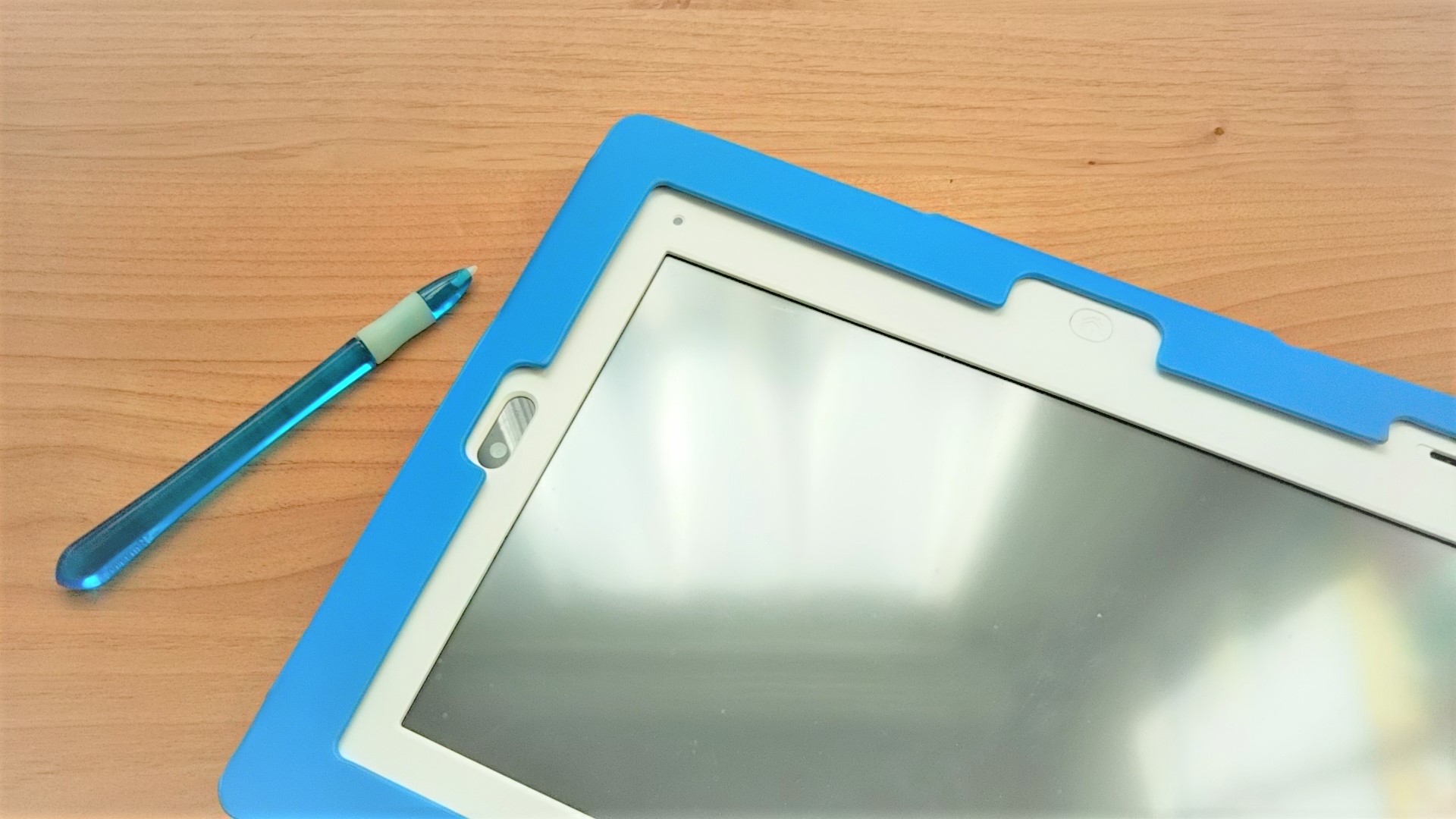
コメント