こんにちは!
6歳差兄弟を育てる2児の母・ひまわりと申します。
朝、子どもが微熱だったり、「だるい」と言っていたりすると、「今日は学校を休ませたほうがいいの?」と悩みますよね。
コロナ禍のいまは、休ませるのが鉄則ではありますが、共働きだと、「なんとか行ってくれないかしら…」と思ってしまうことも。
子どもが体調不良のときの見極め方について、わが家の体験談・失敗談をまとめました。
体調不良で登校を迷うのはどんなとき?
明らかな高熱であれば、迷わず休ませる判断ができますが、実際は、判断に迷う日の方が多いものです。
微熱のとき
37.0~37.2℃くらいの微熱はよくあること。
明らかに平熱よりは高いけれど、それが一時的なものなのか、発熱の兆しなのかを判断するのは難しいです。
「ひとまず登校してみる?…熱が上がったら迎えにいくから!!」と、つい思ってしまうのですが…。
微熱の登校基準は、「いつもやっていることをできるかどうか?」
わが家の場合、「熱」+「本人の元気度」で決めることが多いです。
具体的に観察するのは食欲。朝ごはんを食べられるか?給食は食べられそうか?
長男は給食が大好きなので、「給食、食べられるか分からない…」と回答がきたら、「あ、体調悪いんだな」と判断して休ませることが多いです。
【失敗談】微熱→39℃で保健室に
コロナ前の話ですが、微熱があるけど元気で食欲もあったので送り出した結果、早退となったこともありました。
午前中のうちに保健室から「○○くん、39.2℃ありまして…」と電話をもらい、慌てて迎えにいきました。
担任の先生が、いつもより元気のない様子に気づいて、おでこを触ると激熱で保健室に送還されたとか。
朝の時点で微熱なら、日中に向けて体温が上がっていく可能性の方が高いのも事実。
そして、誤算だったのが、本人が自分の体調の異変(発熱)に気付けなかったこと(それだけ朦朧としていた可能性も…)。
無理をさせてしまったなと反省した出来事でした。
小学校低学年だと、まだ自分で自分の体調を把握することも、それを説明することも難しいです。
無理をさせ過ぎない適切な判断ができるようになるのは親も子も経験の積み重ねが必要です…。
なんか気持ち悪い
微熱と並んで多いのが、「なんとなく気持ち悪い」「なんかだるい」という日。
子どもながらに、いつもと違う感じはするけど、それが何なのか、本人もよく分からないし説明できない。
わが家の場合、登校時間までしばらく横になって様子を見てみます。
それでおさまることもあります。スッキリ起きられなかったり、ちょっとした体調の変化だったり、お腹が空きすぎていただけだったり。
それでもよくならないときは、「お腹の風邪」や「季節の変わり目の体調不良」でした。
お腹の風邪
幼少期から、お腹の風邪で嘔吐することが度々あった長男。
「喉のあたりが変な感じ」「なんか気持ち悪い」という表現のときの半分は、嘔吐を伴う風邪であったケースが多いです。
「吐き気」って、子どもにとっては自覚するのが難しいもの。
実際に吐く経験を重ねながら、「これは吐き気なんだ」と覚えていくようです。
季節の変わり目の体調不良・だるさ
暑い日・涼しい日が交互に繰り返されたりと、季節の変わり目の寒暖差に体がついていけないことで、だるさを伴うこともあるようです。
特に今年は長雨でムシムシする日が多かったり、大人にとっても過ごしにくい日が続いています。
朝ごはんをしっかり食べられなかったので「お腹の風邪で嘔吐になったら…」と用心して休ませませましたが、午前中ゆっくり過ごすことで、徐々に回復。1日様子をみて「これは風邪ではないな」と後から判断しました。
「登校できたかも?」と思えるくらいの軽めの体調不良でしたが、だるさの原因が分からないと、コロナの時期は登校させるのも難しいものです…。
ついやってしまいがちな親の対応
朝、子どもの体調不良と向き合うときに、ついつい、やってしまいがちな対応があります。場合によっては子どもを傷つけることもあるかな…と気を付けるようにしています。
親が不機嫌にならない
子どもから「なんだか調子が悪い」と聞いた途端、「今日の仕事どうしよう」と自分の仕事のことが頭をよぎったり、「こんな日に限って!」という気持ちが顔や態度に出てしまうことがあります。
子どもの体調はもちろん心配だけど、自分自身に心の余裕がなくて焦りが態度に出てしまうのです。
子どもにとっては、ただでさえ体調不良なのに、親の機嫌まで悪くなってはかわいそう。気を付けなければ…と思っています。
子どもを責めない
小学校低学年くらいだと、自分の体調をうまく説明できない場合もあります。
「なんか気持ち悪いような…気がする…」と言われると、登校させてよいものか判断できず、つい責め立てるように「熱は?」「だるさは?」「食欲は?」と聞いてしまいがちです。
責めたいわけじゃないのに、子どもはなんだか責められてるみたい…。
また、休ませた途端、元気になって(元気に見えて)、「そんな元気なら学校いけたじゃない~」とツッコミたくなることも。
でも、家にいられる安心感から元気になることもありますし、朝ゆっくり過ごすことで回復していくこともありますよね。
学校を休むことを親が責め心で対応していると、空気を読む子は「ぼくが休むとお母さんが困る」と無理をしてしまうかもしれません。
一旦休むと決めたなら、たとえ朝の10時にもう元気であっても、「明日からは元気に行けそうだね」と応援してあげられる母でありたい…と思います。
体調不良が心理的なものだったら…?
「休んでもいいんだよ」と安心させてあげる
「微熱」「だるい」「気持ち悪い」と平日の朝に聞くと、「心理的な要因からの体調不良だったらどうしよう…」と不安になることもあります。
仮に、学校生活に行きたくない要因があり、そこから体調不良を起こしているとしたら、親は「休んでもいいんだよ」とまずは安心させてあげることだ、と本で読みました。
決して仮病というわけではないのです。
わたし自身、わが子を見ていて、たまに不安になることがありますが、その対策として、日頃からさりげなく、学校でのことを聞くようにしています。
学童からの帰り道や、翌日の準備をしているとき等に、学校での出来事、授業のこと、休み時間のこと、好きな授業や、面倒くさいと思っていることとか。
たいした情報量でもないし、断片的な情報しかないけど、「あ、この子は学校行きたくないとは思ってなさそうだな、総合的には楽しんでいそうだな」と判断できます。
子どもの様子をよく観察すること。話を聞くこと。仮に何かあっても味方でいること。
親ができることって限られるのだな、と思いつつ、でもその限られたことを地道に続けたいと思っています。
まとめ:子も親も経験を積めば判断しやすくなる
子どもの体調不良との向き合い方は、親も子もある程度回数を経験しないと適切な判断は難しいものだな、と第一子の子育てを通して痛感しています。
もう少し経験値が上がっていけば、親も、「あ、この子がこんな様子の時は、このパターンだな」と分かるようになるし、子ども自身も、だんだん自分の体調を把握して、説明できるようになっていくことでしょう。
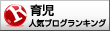

コメント