こんにちは!
6歳差兄弟を育てる2児の母・ひまわりと申します。
次男は離乳食がなかなか順番に進みませんでした。
この記事は、「こんな工夫をしたけど、ほとんど失敗だった!」という生産性のない体験談です。
でも、わが子が離乳食を食べてくれないと悩むママなら「うちの子だけじゃないのね」と安堵できること間違いなし。
よろしければお付き合いくださいm_ _m
離乳食を食べない子は、工夫しても食べない

離乳食を食べない悩みを相談したり検索したりすると、「こんな工夫をしてみましょう」という情報がたくさん得られます。
でも、食べない子って、何をどう工夫しても食べないですよね?
「おかゆのツブツブが嫌なのかも。裏ごししてみては?」
「軽く授乳して空腹を紛らわせてからあげてみては?」
「2週間くらい間をおいて、チャレンジしてみましょう」
次男はどれを試してもダメ。
これがもし、はじめての子のときだったら、「うちの子は何かおかしいのでは…」と、とても不安になったことでしょう。
2番目の子だったおかげで、必要以上に心配せずにいられました。
というか、「大丈夫じゃない」って言われても、食べないんだから仕方がないのです。
ここにまとめたのは、試したけどダメだった体験の数々です。
おかゆを食べさせるための工夫アレコレ

おかゆを食べないと焦ります。日本人の主食ですから。「何をどうしたら食べてくれるのだろう?」と試行錯誤を繰り返しました。
【工夫1】おかゆの粘りをなくす
「おかゆをすりつぶして粘りが出ると飲み込みにくくなります」とは本でもネットでも講習会でも聞く話。
「すりがゆ」を作るとき、確かにおかゆをすり鉢でゴリゴリやると粘りが出ます。だから「軽くたたいてサラッと仕上げるのがコツ」ということなのですが、これがなかなか難しい。
潰そうとしてもご飯粒に逃げられてしまうので、ついゴリゴリしたくなるのです。
ハッキリ言って苦手でした。その上、苦労して作っても食べないんですよね…。
【工夫2】おかゆを裏ごししてツブツブをなくす
「おかゆを嫌がる子はツブツブが苦手な場合も」。これも離乳食本の常套文句。
次男も、とりあえず口を開けてくれても、ご飯粒で「オエッ」となっていました。
すりがゆでは、相当丁寧にやらないとツブツブは残ります。むしろ、ツブツブをなくそうと躍起になっているうちに、おかゆは粘りが出て固くなり美味しくなくなります。
その点、裏ごしすれば、ツブツブは確実になくなります。
しかし、滑らかにしたから食べるということもありませんでした。
それに、裏ごしたおかゆも、結構粘りが出ているような?すりがゆとどっちがいいんだか…。
【工夫3】おかゆの上澄みだけをあげる
ツブツブもトロトロも嫌なら、「上澄はどう?」ということで、お湯だか粥だかわからないような薄いものをあげてみたけど、それも拒否。
次男は全く口を開けてくれなかった訳ではないので、いろんなタイプのおかゆを、味見はしてくれているのです。
でも、その上で、食べなくなるので美味しくないのでしょう。
確かに、味付けもないお粥の上澄みは、美味しくはないです…。
【工夫4】おかゆを土鍋で作る
おかゆはご飯に水を足して作るより、米から炊くと美味しいです。特に土鍋で作るったおかゆは大人が食べても美味しいもの。
「次男がぜんぜんおかゆを食べん」と実家の母にこぼしていたら、帰省の際に土鍋で10倍かゆを作ってくれていました。
母がそれをスプーンで口元にもっていくと、なんと5口くらい食べたのです!
「味の違いの分かる子なのか?」と驚きながらホッとしたのも一時だけ。翌日からはいつもの次男に戻っていました。
後にも先にも、おかゆを食べるのをハッキリと見届けたのはこのときだけ。
自宅に戻ってからも、炊飯器で米から炊いたおかゆを作ってみましたが、ほとんど口をあへませんでした。
【工夫5】おかゆに味をつける
母乳やミルクには甘みがあるので、それに比べて味のしないおかゆを嫌がるという話も聞きます。
そこで、おかゆに鰹節をまぜたり、醤油数滴たらしたり、和風だし風味のベビーフードを試したり。あるいは、カボチャやサツマイモなどの甘みのある野菜を混ぜたりしてみました。
どれも食べませんでした。
【結論】結局おかゆは食べなかった
「日本人だもの、お米の主食は食べれるようにしないと…」という意識もあって、あの手この手で試すこと数か月。
でも、どれもおかゆをスムーズに食べはじめるきっかけにはなりませんでした。
長男はパクパク食べていたから、わたしの作るものが特別にまずい…とかそううことではないはず…(と願いたい)。
【工夫6】ミルクを混ぜてみる

おかゆ以外のものも、ほとんど拒否していた次男。
味付けなしでもほんのり甘いカボチャやサツマイモは、ハードルが低そうに思えたので、おかゆをある程度試したところで、いも・野菜類に移りました。
でもカボチャやサツマイモのペースト、食べないんですよね。
そこで「慣れた味に近づけたらどう?」と思ってペーストにミルクを混ぜてみました。もはや簡単なデザートで味は悪くないのですが、興味なしでした。
【工夫7】市販の離乳食を使ってみる

手作り離乳食を食べてくれないときは、味、食感ともに研究しつくされたベビーフードに頼ってみるのもひとつ。
おかゆ、野菜や魚のペーストなどなど、いろいろ試してみましたが、リピートしてくれたのは、コーンスープや果物ゼリーなどごく一部。
煮込みうどんや炊き込みご飯など、いかにも美味しそうなものも興味を示さず。
【工夫8】少し授乳してから食べさせる

離乳食よりも母乳を欲しがる赤ちゃんには、「少しだけ母乳やミルクを飲ませて落ち着かせてから離乳食をあげても」というアドバイス。よく実践してみました。
でも、それで「食べたくないものを食べるようになった」ということもありませんでした。
飲む前でも後でも、せんべいとかは喜んで食べました。そして胃の容量オーバーで吐くという…。
【工夫9】スプーンを替えてみる

「赤ちゃんが食べないときは、スプーンを替えると食べることもあります」
これもとてもよく言われること。
そこで、親戚中から集まった、役目を終えた離乳食スプーンを試してみたのですが…、「この子が食べないのはスプーンの問題ではない」と分かりました。
でも、赤ちゃんが食べやすいスプーンは確かにありました。普通の幼児用のスプーンでは赤ちゃんの口に対して大きすぎるので、ヘラのような、深みのないフラットなタイプを愛用していました。
【工夫9】食べさせる人を替えてみる
わたしが食べさせようとするから、おっぱいを飲みたがるのかも…。と思ったので、主人がいるときは、食べさせる役目をお願いしてみました。
これは、「お、上手くいった…?」と思うことも少しありました。でも、とっても気まぐれ。
【その後】離乳食、食べるようになった?
そんな次男はもうすぐ1歳半。結局、食べるものは食べるけど、食べないものは食べません。
それでも、奥歯が生えはじめた1歳ごろから、少しずつ「ごはん」を食べるようになり、1歳半に近づく頃には「おにぎり」を食べるようになりました。
「おかゆ」を食べなくたって、半年後には、ちゃんと「ごはん」を食べるようになっていた。
それでいいじゃない、と思いました。
【食べるもの】 ・主食…おにぎり、うどん ・たんぱく質…豆腐 ・乳製品…ヨーグルト、牛乳 ・果物…りんご、いちごジャム ・おやつ…せんべい
【食べるメニュー】 ・麻婆豆腐 ・カレーライス
定番の献立は、「味噌汁に入れたうどんと豆腐」「おにぎり」「煮リンゴ」「ヨーグルト」。
たまに、大人のメニューに合わせてカレーや麻婆豆腐を食べています。
野菜や魚を並べても手でよけるので、おにぎりにひそませています。
【分かったこと1】個人差があるのは当たり前
あの手この手でおかゆを食べさせようとしたわたしですが、0歳児に、型通りであることを求めているなぁと思いました。
たとえば、泳げるようになる、自転車に乗れるようになる、縄跳びが飛べるようになる、逆上がりができるようになる。こういったものは、幼稚園、保育園時代にできる子もいれば、小学校にはいってからという子もいる。1年、2年、あるいはもっと個人差があるのは当然です。
でも、0歳児って、「5~6か月頃から離乳食をはじめましょう」と書いてあったら、それ通りにいかないと、不安になったりします。
まわりと、たった数か月成長に差があるだけで不安になったりします。
でも、人生長い目でみれば、ほんとうに1ミリ違うかどうかの差でしかないのではないでしょうか。
もっと、どっしり構えておおらかにしていてもよかったなと振り返っています。
【分かったこと2】親が悩んでも仕方がない
イギリスのことわざに、「You can take a horse to the water, but you can’t make him drink.(馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない)」というものがあります。
離乳食も一緒だなと思いました。
親は、子どもが食べるように工夫して導くことはできるけど、それを食べるか食べないかは赤ちゃん本人でないと分かりません。
親の役目は食べやすい環境を作ってあげるところまで。その先は悩んでも仕方がないのだと思います。
【分かったこと3】年配の方と話すと安心できる
悩んだり焦ったりするときは、年配の方とお話しすると、「そんなに気にしなくていいんだ」って思えることが多かったです。
親や地域の保健師さん、子育て支援センターの保育士さん。
「いとこの〇〇ちゃんは、プリンしか食べなかったんだって」とか、
「体重が増えてれば大丈夫よ」とか、いろいろな話を聞けると思います。
わが子の現状は変わらなくても、親が安心できることは、大切だと思います。
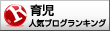
合わせて読みたい


コメント